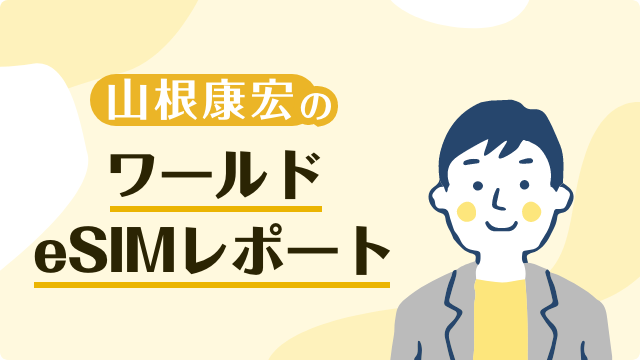pSIMって何? eSIMとの違いは? SIMカードの歴史と種類
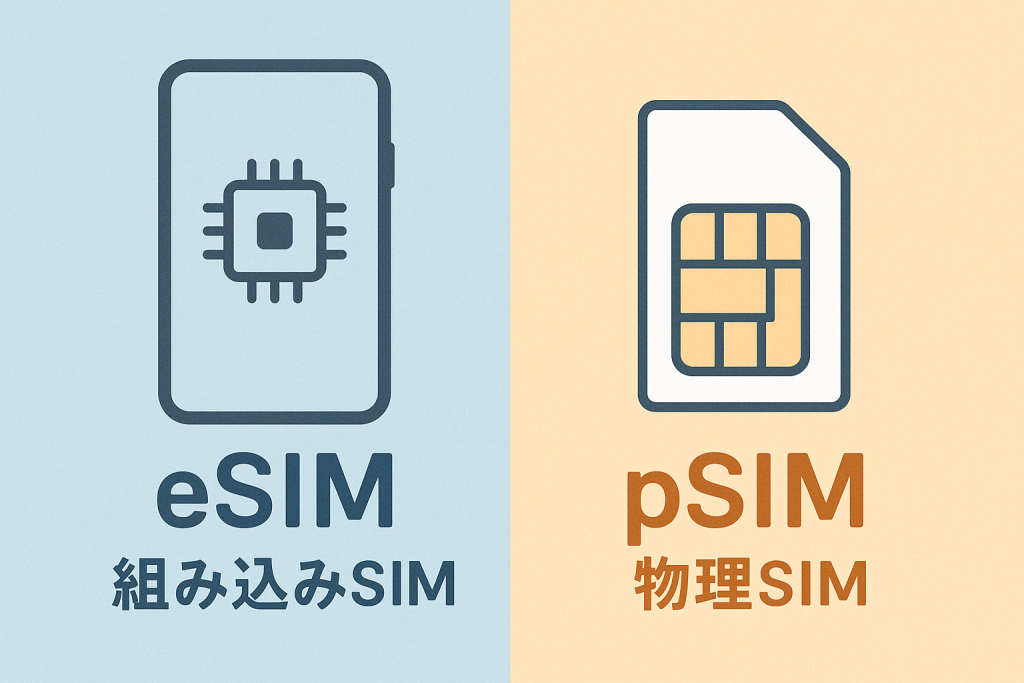
最近、「pSIM」という用語を急に見かけるようになりました。pSIMは従来からあるSIMカード(物理SIM)のことで、eSIMの普及に伴い、eSIMと区別するために慣用的に使われ出したものと思われます。
目次
pSIMとは?
pSIMとは、「physical SIM(物理SIM)」の略です。スマートフォンの中に差し込む、小さなカード型のチップのことで、モバイル通信キャリア(ドコモ、au、ソフトバンクなど)から発行されます。そもそも「SIMカード」と呼ばれ、長い歴史があります。SIMカードには、IMSI(International Mobile Subscriber Identity)と呼ばれる固有の番号が付与されており、これと電話番号を結びつけることにより通信を可能としています。
「pSIM」という用語が急に広まりだした背景
以前は単に「SIMカード」と呼ばれていましたが、近年普及している「eSIM(イーシム)」と区別する必要が出てきたことで、「pSIM」という言い方が急速に使われ始めました。特に、以下のような背景があります
• iPhoneやGoogle Pixelなど主要機種でeSIM対応が標準化されたこと
• 海外ではeSIMオンリーのスマホ(物理SIMスロットなし)が出てきていること
• 通信契約や乗り換えがオンラインで完結するなど、eSIMの利便性が注目されていること
こうした流れの中で、「従来のSIMカード」のことをeSIMと区別するために「pSIM」と呼ぶようになったのです。
pSIMとeSIMの違い
pSIMとeSIMの違いを一覧にしてみました。
| 項目 | pSIM(物理SIM) | eSIM(組み込みSIM) |
| 形 | カード型で、スマホに差し込む | 本体に内蔵されたチップで、取り外し不可 |
| 入れ替え | 手で抜き差しして交換 | スマホ上の設定で切り替え可能 |
| 利便性 | 店舗での契約・発行が中心 | オンラインで完結、即日利用が可能 |
| 紛失・破損のリスク | 小さいため紛失や破損の恐れあり | 内蔵型のため物理的リスクなし |
| 機種変更時の扱い | SIMカードを差し替えれば移行可能 | プロファイルを再発行または転送が必要 |
表 pSIMとeSIMの違い
pSIMの種類
「SIMカード」として1991年に登場して以来、長い歴史があります。進化の中で小型化も進んできました。近年は「ナノSIM」が主流です。また、デュアルSIM端末(2回線を同時に使用できる端末)では、pSIMとeSIMを組み合わせて使うことができる機種が増えてきました。
pSIM(SIMカード)の種類は以下の通りです。
• フルサイズのSIM
→ クレジットカードサイズ(幅85.6mm×高さ53.98mm×厚み0.76mm)の接触型ICカードで、1991年に登場
• ミニSIM(標準SIMとも呼ばれます)
→ カードの外形寸法は幅25mm×高さ15mm×厚み0.76mmで1996年に登場
• マイクロSIM
→ カードの外形寸法は幅15mm×高さ12mm×厚み0.76mmで2003年に登場
• ナノSIM
→ カードの外形寸法は幅12.3mm×高さ8.8mm×厚み0.67mmで2012年に登場。現在の主流

左からミニSIM(標準SIM)、マイクロSIM、ナノSIM

最初期のSIMカードはクレジットカードサイズで、カードサイズのまま挿入して使用する端末もあった(写真はイリジウム9500/1998年発売、市販最後のフルサイズSIMカード対応端末)

最近はどのサイズのSIMとしても使用可能なマルチカットSIMが発行されるケースが多い
今後pSIMはどうなっていくのか
将来的には、pSIMは徐々に減少していくと考えられています。
理由としては
• eSIMの方が利便性・セキュリティ面で優れている
• メーカー側も物理スロットを省くことでスマホ内部の設計が自由になる
• 海外ではすでにeSIMオンリーの端末(例:iPhone 14米国版など)も登場
• MNP(番号そのままで乗り換え)や契約変更もオンラインで完結できる
などの理由が考えられます。ただし、すぐにpSIMが完全に廃れるわけではありません。日本ではまだ多くの利用者がpSIMを使っており、当面はpSIMとeSIMが併存する時期が続くでしょう。
ちなみに、pSIMは日本特有の用語の使い方のようです。海外(英語圏)では「pSIM」という用語は一般的ではありません。eSIMとの区別が必要なときは「physical SIM」や「removable SIM」などと表現されます。たとえば、AppleやGoogleの公式サイトでも「pSIM」という表記はほぼ見られません。
いっぽう日本ではeSIMの普及に伴い、2025年に入ってから「pSIM」という略称が急増してきました。eSIMとセットで「eSIM/pSIM対応端末」などと記載されるケースも増えているようです。
pSIMとeSIMの普及状況の違いは以下の通りです。
| 項目 | 海外(特に北米・欧州) | 日本 |
| eSIM対応スマホの普及 | かなり増加(iPhone 14以降はeSIM専用) | 増加中だが、pSIMスロット併用が主流 |
| eSIM単体契約のしやすさ | オンライン契約が主流 | 一部キャリアではまだ手続きが煩雑 |
| pSIM中心の文化 | 徐々に縮小(SIMスロット廃止も) | まだpSIMが一般的 |
表 pSIMとeSIMの普及状況の違い
まとめ
用語の定着度と普及ペースに差が!
• 「pSIM」という用語自体は日本独特の区別表現で、eSIMとの棲み分けの中で生まれた言葉です。
• 海外では「physical SIM」「SIM card」といった正式な表現のままであり、pSIMという略称はあまり見られません。
• eSIMの普及スピードや、通信契約の文化などにより、国ごとに明確な違いがあります。
名桜大学人間健康学部健康情報学科教授。’90年代から携帯電話端末のレビューやサービスの解説を行ってきた。携帯電話情報サイトの編集長などを務めた後、2009年に大学教員に転身。以後スマートフォンの社会での活用などを研究テーマとして活躍。現在は医療・ヘルスケア分野へのデジタルデバイスの応用を中心に研究に従事。携帯電話コレクターとしても知られる。